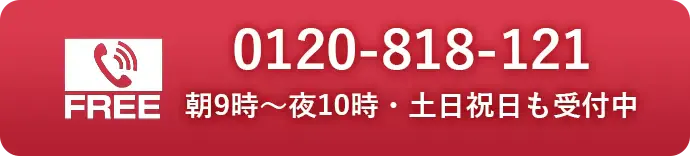- 交通事故によってケガをした被害者は、どのような請求ができるのでしょうか?
-
交通事故によりケガをした場合には、主に次のような様々な損害につき、賠償金を請求することができます。
治療費、付添看護費、入院雑費等
実際に病院に通った場合にかかる費用などです。
休業損害
会社を休まなくてはならなかった分の給与相当額などです。
入通院慰謝料
ケガをして、病院に入院したり、通院したりしている間に受ける「痛い」「辛い」という精神的苦痛を賠償するものです。
後遺障害による逸失利益
後遺障害が残ってしまった場合に、将来の労働能力に影響を及ぼすものとして、その分の賠償となります。
後遺障害慰謝料
後遺障害が残ってしまったことに対する精神的苦痛を賠償するものです。
- 交通事故によりPTSDと診断されました。損害賠償を請求できますか?
-
請求できる場合はありますが、困難であるのも実情です。事故後、PTSDに陥ってしまったという事例について、裁判例でも、損害賠償を認める場合と認めない場合があります。
PTSDが後遺障害にあたると判断されれば、事故によって収入が減るだろう部分については損害賠償を請求できますし(逸失利益)、精神的な苦痛の賠償を求めることもできます(後遺障害慰謝料)。しかし、PTSDを交通事故による後遺障害として認めてもらうには、さらに、事故との因果関係が問題となります。通常の一般人は、私生活上それなりのストレスは感じているのが実情で、PTSDという診断が出ても、それが交通事故を原因とするものか、因果関係の証明が困難となっています。またその程度が重大なもので永久に残るものなのかどうかも問題となります。
実際に裁判で争われたケースでは、後遺障害と認められない場合が多いのもまた実情であり、PTSDの症状につき、保険会社にどこまで賠償してもらえるかは、交渉次第・裁判次第ということになります。
- 家族が交通事故にあい、後遺症が残ったことで将来を悲観して自殺してしまいました。損害賠償を請求できますか?
-
請求できる可能性はありますが、自殺した原因が事故にあること(因果関係)を証明する必要があり、因果関係を証明することができない場合には、残念ながら死亡慰謝料や逸失利益(自殺しなければ得られたはずの収入等)を請求することはできません。
また、因果関係を証明することができたとしても、本人の精神状態が寄与したとして、相応の減額がなされる可能性があります。
- 加害者に弁護士費用を請求することはできますか?
-
交通事故の裁判の場合、あなたが負担した弁護士費用相当額が損害として認められることがあります。
もっとも、損害として認められるのは、あくまで弁護士費用「相当額」であり、現に支払った弁護士費用全額が必ずしも損害として認められるわけではありません。裁判例の傾向としては、認められた賠償額の1割程度の金額を、損害賠償額として認めるものが多数となっています。
- 私は長距離トラックドライバーですが、症状固定の判断を受けた後も痛みが残り、運転が不安です。どうしたらいいでしょうか?
-
後遺障害につき等級の認定が出れば、後遺障害による慰謝料や逸失利益を請求することができますので、まずは後遺障害診断書を作成してもらい、任意保険会社(事前認定の場合)あるいは自賠責保険会社(被害者請求の場合)に必要書類を提出してください。
- 成年の兄が交通事故によって植物状態になってしまいました。 賠償請求をするにはどうすればいいですか?
-
交通事故の被害者が植物状態になってしまった場合には、被害者自身が話をしたり、自分の意思を伝えたりすることが困難となります。したがって、被害者の方に代わる代理人を立てる必要が生じます。
この場合、通常は、家庭裁判所に対し、「後見開始の審判」を申立て、「成年後見人(代理人)」を選任してもらい、その後見人もしくは後見人から選任された弁護士等が、保険会社に対して損害賠償請求を行うことになります。「後見開始の審判の申立」は、被害者の配偶者や4親等以内の親族(両親・祖父祖母・子供・孫・兄弟姉妹・甥姪・従妹等)であれば申立てができます。詳しいことは、裁判所Webサイト:後見開始に申立手続の説明や書式ダウンロード・申立書記載例等の案内があります。また、最寄りの家庭裁判所に電話すれば、一般的なことは教えてもらえますし、申立書などのひな形やパンフレットの備え付けもされています。
- 加害者が事故で死亡した場合も、損害賠償は請求できますか?
-
加害者が死亡した場合でも、加害者に対する損害賠償請求権は消滅しないため、損害賠償請求をすることは可能です。
事故当時に加害者が任意保険会社に加入している場合は、保険会社が保険金の支払義務を負っています。したがって、通常は、加害者が死亡した場合であっても、引き続き、任意保険会社に対して損害賠償を請求していくこととなります。事故当時に加害者が任意保険会社に加入していない場合は、加害者の相続人(遺族)に損害賠償請求をします。ただし、相続人が相続放棄をすると相続人に対して損害賠償を請求することはできません。
この場合には、下記のような対処法があります。- 加害者側の自賠責保険に「被害者請求」で直接請求する
- 国の救済措置の「政府保証事業」という制度を利用する
- 被害者自身が加入し往復ている任意保険の「人身傷害保険」「搭乗者傷病保険」利用する
など
- 父が交通事故で死亡しました。相続放棄をしたら損害賠償は受け取れなくなりますか?
-
事故により発生する損害賠償請求権は、【1】亡くなったお父様自身の損害賠償請求権(精神的損害である慰謝料・将来仕事により得られるべきであった収入などの逸失利益など)と、【2】あなた自身の損害賠償請求権(慰謝料など)となります。
相続により放棄するのは、【1】お父様自身の損害賠償請求権などの相続財産だけですので【2】あなた自身の有していた損害賠償請求権について請求することは可能です。しかしながら、通常は、被害者であるお父様自身の損害賠償額が極めて高額となることが予想され、裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)では慰謝料部分でも2,000万円以上となる可能性が高く、相続放棄をしてしまうと、本来受けるべき損害賠償請求権の大半が請求できなくなる可能性があります。相続放棄をすべきか否かについては、お父様の相続財産の資産状況・負債状況を精査して、慎重に判断すべきことになります。
- 加害者以外には、損害賠償を請求できないのでしょうか?
-
たとえば、以下のような人たちに、請求できる場合があります。
- 車の所有者
- 労務中の事故である場合には、加害者の勤務先社長や雇用主
- 相手方が未成年である場合には、加害者の両親
- その他、加害者以外にも交通事故の原因となる行為をした人
- 道路の管理に手落ちがあった場合には、国・地方公共団体等
- 加害者は、レンタカーを運転中の学生でした。 レンタカー業者に損害賠償を請求できないのでしょうか?
-
請求できる可能性があります。
交通事故では、自動車損害賠償保障法という法律で、加害者以外にも損害賠償責任を請求できる場合を定めています。大まかにいえば、【1】自動車の運行に対して支配を及ぼすことができ、制御すべき立場にあり、【2】その者のために運行がなされていると評価できる場合、加害者以外であっても責任を負う場合があるのです(これを以下「運行供用者責任」といいます)。レンタカー業者は、これに当てはまるケースが多いですが、具体的事情によっては責任を否定されている裁判例もあります。レンタカー業者への請求を実際に検討なさっている方は、ぜひご相談ください。
なお、レンタカーによる事故が発生した場合、交通事故証明書には、そのレンタカー業者が自動車の所有者として記載され、連絡先も記載されます。したがって、損害賠償を請求する場合には、その記載を手掛かりに、レンタカー業者の加入する保険会社や、レンタカー業者に対し交渉することになります。
まずはお気軽にご相談ください。
朝9:00 ~ 夜10:00・土日祝日も受付中
0120-818-121