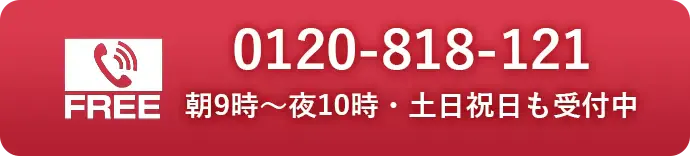- なぜ後遺障害の等級認定の申請をする必要があるのですか?
-
交通事故のケガにより「後遺障害」が残った場合には、後遺症慰謝料を請求することができますが、その請求に「後遺障害の等級が認定されること」が必要だからです。
交通事故などによりケガをした場合、治療しても完全には回復せずに、身体や精神の機能に不完全な状態が残ることがあります。これを「後遺症」といいますが、後遺症が残ったと主張するだけでは後遺症慰謝料は請求できません。後遺障害の等級認定は自賠責保険の支払基準となるもので、自賠責保険は認定された等級に基づいて後遺障害の逸失利益や慰謝料の賠償額を算定します。
また、自賠責保険に限らず、任意保険会社や裁判所においても、原則として認定された等級に基づいて賠償額を算定します。このように、後遺障害の等級認定は賠償額に非常に大きな影響をおよぼします。
適切な等級認定がなければ、適切な賠償額を得ることは難しいため、後遺障害の等級認定の申請をする必要があるのです。
- 後遺障害の等級認定は、いつ申請すればよいですか?
-
後遺障害とは、治療による回復が望めなくなった状態(症状固定)で残ってしまった症状のことですから、症状固定となった後に、後遺障害の等級認定を申請することになります。
- 症状固定は、誰が判断するのですか?
-
症状固定かどうかを判断するのは主治医です。
症状固定とは、これ以上治療を行っても症状の回復が見込めない状態のことをいいます。一般的に、加害者の保険会社は「症状固定ですので、今後は治療費の支払いを打ち切ります」などと言ってくることが多いですが、保険会社はあなたの症状の状況を直接見ているわけではありません。
実際にあなたの症状を見ている主治医が症状固定日を判断するべきです。
また、保険会社の打診する打ち切り日が必ずしも症状固定となるわけではないため注意が必要です。
ただし、主治医であっても症状固定の判断は難しい問題であり、裁判所の判断する症状固定日と主治医の判断する症状固定日が必ずしも一致するわけではありません。
適切な症状固定日を判断してもらうためには、主治医に症状の内容をしっかりと伝えていただき、あなたの体の状況をよくわかっていただくことが重要です。
- 弟(成人しています)が交通事故によって植物状態(遷延性意識障害)になってしまいました。弟の受けた損害について賠償請求をするにはどのようにすればよいのでしょうか?
-
交通事故の被害者が植物状態(遷延性意識障害)になってしまった場合、被害者自身が話をしたり、自分の意思を伝えたりすることはできなくなってしまいます。
その場合、被害者に代わる代理人(成年後見人の選任)を決めなければ、被害者に代わって損害賠償をすることはできません。成年後見人の選任をするためには、家庭裁判所に対し、「後見開始の審判」を申立て、「成年後見人」を選任してもらう必要があります。そして、成年後見人もしくは成年後見人から選任された弁護士等が、加害者や保険会社に対して損害賠償請求を行うことになります。
後見開始の審判の申立は、被害者の配偶者や4親等以内の親族(両親・祖父祖母・子供・孫・兄弟姉妹・甥姪・従妹等)であれば申立をすることができます。当事務所では成年後見人選任の申立から保険会社への賠償金請求まで一貫してフルサポートしております。交通事故をご依頼いただく方については、成年後見人選任の申立に関する特別な費用はいただいておりません。ご不明な点があれば、どうぞ遠慮なくご相談ください。
- 後遺障害認定の申請は誰がするのですか?
-
後遺障害の等級認定の申請手続は、損害保険料率算出機構に対して行うのが一般的です。
申請手続の方法としては、加害者の保険会社を通じて行う「事前認定」という方法と、被害者自身(代理人の弁護士含む)が行う「被害者請求」の方法があります。「事前認定」は、保険会社を通じて行いますので手間がかからないというメリットがあります。しかし、提出する資料を被害者の方や弁護士がチェックすることはできません。保険会社にとっては、等級が上がればその分だけ支払う賠償金が増えてしまいますので、より高い等級の認定を受けることに、必ずしも協力的ではありません。場合によっては、不当に低い認定になってしまうおそれもあります。
「被害者請求」は、被害者の方が自ら資料を収集・提出するなどの負担もありますが、提出する資料を被害者自身や弁護士がチェックできるなどのメリットがあります。
弁護士に依頼した場合には、希望があれば弁護士が後遺障害の認定が適切になされるような資料や書類を揃えて、申請を行います。また、仮に最初の申請で後遺障害が認定されずに「非該当」となってしまった場合であっても、「異議申立」を行うことで等級認定の獲得を狙います。
- 後遺障害の異議申立に回数制限はありますか?
-
損害保険料算出機構が行った等級認定に対して異議申立を行う場合には、回数制限はありません。何度でも異議申立をすることができます。
いっぽうで、自賠責保険・共済紛争処理機構に対しては、等級認定の再申請や異議申立を行うことはできません。そのため、認定結果に不服がある場合には、裁判によることになります。
- 後遺障害認定は誰がどのように判断するのですか?
-
後遺障害の認定の判断は、損害保険料率算出機構(加害者側の保険会社が加盟している場合)や自賠責保険・共済紛争処理機構が行います。
損害保険料率算出機構や自賠責保険・共済紛争処理機構の判断は、基本的に後遺障害診断書などの書面に基づいて審査されます。そのため、診断書の記載が曖昧であったり、必要な検査結果の添付が不足していたりする場合には、適切な認定が受けられない可能性があります。認定を得るためには、認定の具体的な基準を踏まえたうえで、適切な書面と資料を提出します。これには、医学的にも法律的にも非常に高度で専門的な知識や経験が必要となります。
そのため、交通事故被害の対応実績が豊富で、後遺障害に詳しい弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
まずはお気軽にご相談ください。
朝9:00 ~ 夜10:00・土日祝日も受付中
0120-818-121