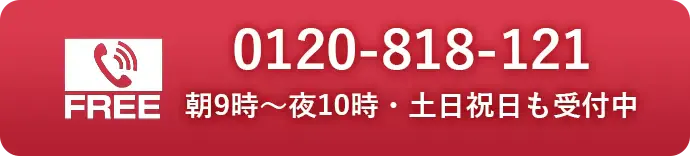- 示談交渉は、いつ始めればよいのでしょうか?
-
通常は治療が終わったときです。
それまでは、治療費や入通院慰謝料等の損害が日々発生し続けているので、損害額の全体がわからないからです。しかしながら、たとえばあなたが大変経済に苦しい状態にあって、治療費や休業損害がすぐに支払われないと来月の家賃が払えないとか、ローンの返済が滞るといった場合もあります。そのような場合は、正式な示談に先立って、もらえなくなった給料分だけ前倒しで払ってください、という交渉を、治療が終わらない段階で行うこともあります(これを「内払交渉」といいます)。
- 保険会社の提示してきた示談金額が妥当なのかわかりません。
-
治療費や通院交通費についてはともかくとして、入通院慰謝料、休業損害、後遺障害による慰謝料、あるいは逸失利益といった項目については、専門家でなければ判断がつきにくいところです。保険会社は、裁判になった場合に認められる正当な損害賠償額よりも低い額しか提示してこないことがよくあります。最終的に示談してしまう前に、金額の妥当性については、交通事故に詳しい弁護士に相談したほうがよいでしょう。
- 交通事故にあい、加害者から調停を申し立てられて裁判所から呼び出し状が届きました。どうすればいいですか?
-
裁判所から呼び出し状が届いたら、無視せず早急に対応するようにしましょう。
病気など、出頭できない理由がある場合には、医者の診断書などを添え、事前に裁判所へ連絡するのが賢明です。
交通事故で裁判所から呼び出し状が届くのは、以下のような場合です。- 民事調停が行われる場合
- 民事裁判が行われる場合
- 刑事裁判が行われる場合
いずれの場合でも、裁判所からの呼び出しを無視するとご自身に不利益が生じますので、注意が必要です。
また、相手方がわざわざ申立てをしてきている以上、対応が複雑になる可能性が高いため、早い段階で弁護士に相談いただくことをおすすめします。
- 交通事故紛争処理センターを利用している最中ですが、手続が自分の思い通りに進みません。弁護士に依頼する意味はありますか?
-
紛争処理センターは、あくまでも第三者として中立的な立場で、和解のあっせんを行うための機関ですので、申立人(被害者)は自分で準備を尽くさなければなりません。
そのため、紛争処理センターに提出する立証資料を検討して選別したり、紛争処理センターの嘱託弁護士や相手方と話し合ったり、審査会で主張したりするなど、紛争処理センターでの手続の最中でも、弁護士にご依頼をいただく意味は、たくさんあります。費用面についてお話しますと、紛争処理センターの利用は基本的には無料です。これは、紛争処理センターの運営資金が、各損害保険会社から拠出されているからです。そのいっぽうで、弁護士に依頼をすると弁護士費用がかかりますが、自動車保険や火災保険には「弁護士費用特約」が付いていることも多いので、弁護士費用特約が付いている場合には、弁護士費用を気にすることなく、弁護士に依頼することができます。
- 交通事故紛争処理センターを利用するか、それとも、弁護士に依頼するかで迷っています。どちらがよいのでしょうか?
-
紛争処理センターで示談のあっせんをしてくれる嘱託弁護士は、あくまでも第三者として中立的な立場で、加害者と被害者の間に介入します。そのため、あなたが受けた損害の立証の手助けをしてくれるわけではありませんし、あなたの主張を代弁してくれるわけでもありません。
いっぽうで、弁護士に依頼すれば、証拠資料の収集から相手方との交渉まで、首尾一貫してあなたの立場に立って、お力になることができます。どうぞお気軽にご相談ください。
- もし訴訟になった場合、訴訟費用はどれくらいかかるのですか?
-
一般的に、訴訟になった場合は、収入印紙代、予納郵券代、交通費、日当が別途かかります。訴状には、収入印紙を貼るのですが、その印紙代は、訴訟の請求額(訴額)によって異なります。
たとえば、請求額が300万円の場合は、2万円の収入印紙代がかかります。予納郵券代は、各裁判所によって金額が異なりますが、相手方(被告)1人につき6000円程度です。このほかに、もし弁護士に訴訟を依頼していれば、弁護士が裁判所に行くための交通費や日当なども別途かかることがあります。
- 交通事故の訴訟では、どのような解決の方法があるのですか?
-
示談交渉や調停などで解決に至らなかった場合や、解決の見通しが立たない場合には、裁判所に訴訟を提起することになります。訴訟では、大きく分けて2つの解決方法があります。最終的に裁判所から下される「判決」によって決着する場合と、訴訟の途中で「和解」することによって解決が図られる場合です。
まず、判決とは、訴訟の手続を終えて裁判所が決めた結論のことで、不服がある場合は上級裁判所に「控訴」(第一審の判決に対する不服申立て)や「上告」(控訴審の判決に対する不服申立て)をして訴訟の手続を再度行うことになります。控訴や上告をしなければ、一定期間を経て判決が確定するため、被告側(通常は交通事故の加害者側)は、これに従う義務が生じます。次に、和解とは、双方が譲歩して合意して争いを終わらせることで、「示談」も広い意味での和解です。特に裁判所で行う和解を「裁判上の和解」と呼びます。裁判上の和解が単なる和解と異なる点としては、裁判上の和解で決められたことを守らない場合には強制執行が可能であることが挙げられます。したがって、裁判外での和解に比べて強い拘束力があります。
交通事故訴訟の多くは、和解によって解決されています。実際に平成24年度の東京地裁民事第27部(交通事故の専門部)においては、全案件の約67.2%が和解で解決しているとのことです。(「民事交通事故訴訟 損害賠償算定基準2014年版 下巻『最近の東京地裁民事交通訴訟の実情』より」)
訴訟は、鑑定や尋問などの証拠調べの手続があるため、医学的な面で争いがあるケースや事故状況について認識に食い違いがあるケースなどに適した手続といえます。しかし、ほかの手続と比べて時間がかかり、最低でも6ヵ月程度、複雑な内容のケースであれば2年ぐらいかかることもあります。
- 入通院慰謝料など傷害部分について先に示談をしてしまい、後遺障害部分は、後で別途協議するというような示談は可能ですか?
-
加害者側の保険会社の対応にもよりますが、可能な場合があります。その場合には、傷害部分の示談の際に、「後遺障害部分は別途協議して請求できる」といった文言を入れるなどして、後で後遺障害部分についても損害賠償を請求できるようにしておくことが、非常に大切です。
また、後遺障害の認定結果次第では、入通院慰謝料(傷害慰謝料)の計算方法が変わる場合がありますし、保険会社も後遺障害の認定結果次第では、態度を変えることが頻繁にあります。そのため、入通院慰謝料など傷害部分を先に示談した方がよいのか、後遺障害の認定を待ったほうがよいのかといった判断は、そのつど慎重な検討が必要です。
示談交渉についてご不明な点があれば、弁護士に相談するのがよいでしょう。
当事務所では、交通事故のご相談は何度でも無料です。
- 示談後に痛みや後遺症が出たら、あらためて損害賠償を請求できますか?
-
通常は、示談成立後に追加で損害賠償を請求したり、示談内容を撤回することはできません。
しかしながら、示談のときに予測不可能だった痛みが発生した場合には例外的に請求が認められるケースがあります。示談時に予測することができなかった損害が発生した場合
示談書に後遺障害部分については別途協議するなどの文言があるケース
ただ、これは極めて例外的な事例ですので、そう簡単に示談の内容をひっくり返すことはできないと考えておいたほうが無難です。
ですから、示談をする際には、本当にその内容で問題がないかをしっかり調べて考え、すこしでも不安があるときは弁護士の意見を聞いたうえで損をしない示談をすることをおすすめします。
- 示談すると、加害者の刑事事件に影響するのでしょうか
-
加害者にとって有利な事情として考慮されることがあります。
加害者の弁護人が示談書を証拠として裁判所に提出することで、加害者に裁判所から言い渡される刑罰が軽くなることがあります。そのため、加害者がとくに刑事事件で身体拘束を受けている場合、親族などが必死で示談してもらいたいと働きかけてくることがあります。しかしながら、刑事事件の判決が確定した瞬間手の平を返したように冷たい態度を取られたりして、被害者のほうがさらに辛い思いをする、というような事例もあります。ですから、加害者が刑事事件にかかっている最中に示談などをするときは、その真意を見抜くことが大事です。
まずはお気軽にご相談ください。
朝9:00 ~ 夜10:00・土日祝日も受付中
0120-818-121